 健康
健康 悪い脂摂ってませんか?
摂取すると身体に良い働きをする脂と、良くない働きをする脂があります。脂肪肝へのリスクに焦点をあてて、整理してみましょう。脂肪肝とは肝臓は余分な糖を脂肪に変えますが(中性脂肪)、この脂肪が肝臓にたまり脂肪肝になります。ただ、脂肪がたまっている...
 健康
健康 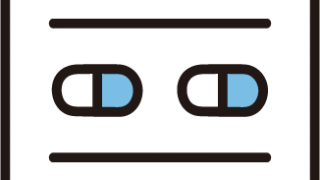 健康
健康 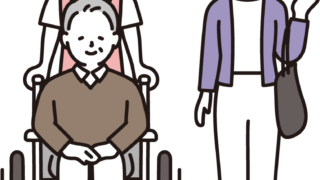 健康
健康  健康
健康  健康
健康  健康
健康  健康
健康  健康
健康 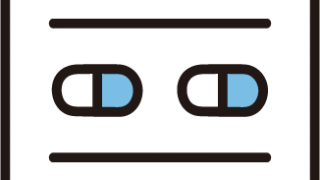 健康
健康 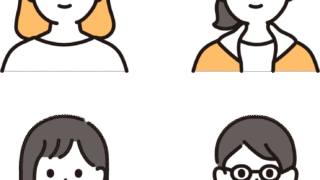 健康
健康