〜シリーズ2 腸と睡眠〜
こんにちは。
薬剤師歴20年以上、子育て真っ只中の薬剤師たまさんです。
今回は、腸と睡眠の関係についてお話します。
なぜ睡眠かというと、某メーカーの某乳酸菌飲料が睡眠の質を高める、という噂があるからです。
その根拠はあるのでしょうか?
結論的には、根拠といえるものは特になく、治療につなげられるような医学的なエビデンスは乏しい、ということになります。
でも、根も葉もない、というわけではなさそうです。
近年「脳腸相関」という言葉が使われるようになりました。腸と脳は深い関わりがあります。
ストレスで胃が痛い、下痢する、などは昔からよく聞きますね。胃や腸のような消化器官は脳の状態の影響を受けることはよく知られていました。少なくても、無関係ではないことがわかります。
中でも、セロトニンの働きについて注目されています。
セロトニンは、体内で作られる成分ですが、「幸せホルモン」と言われ、意欲や気持ちの安定に作用します。睡眠にもとても関与します。このため、うまく働かないと抑うつ傾向の原因になります。
このセロトニン、実は大半が腸で作られます。もちろん脳でも作られますが、たったの5%にしか過ぎません。
よく言われているのが、セロトニンは腸で沢山作られるから、腸内環境を整えると心の健康に良い、ということです。逆に、腸内環境が乱れていると、心が不安定になってしまう、と言われています。
ところが、これは正しい解釈ではありません。
実は、腸内で作られるセロトニンは、脳には届きません。脳はとても大切な器官なので、さまざまな成分に暴露されないように、「血液脳関門」という機能により、通ってよいものをふるい分けしています。腸内で作られたセロトニンは、ここを通ることができないのです。
腸内で作られたセロトニンは、気持ちに働くのではなく、腸のぜん動運動を整えたり、骨の形成に役立ったりしています。
では、腸が気持ちや睡眠に関わるというのは間違いなのでしょうか?
いいえ、ちゃんと関わりがありますので、お話します。
セロトニンは、牛乳等に含まれる必須アミノ酸であるトリプトファンという成分から作られる代謝産物です。
そして、なんと、セロトニンの前段階のトリプトファンは、血液脳関門を通ることができるのです。腸で吸収されたトリプトファンの一部は、血液にのって血液脳関門を通り脳内へ移行し、脳内セロトニンを作ることができます。脳内で作られたセロトニンは、「幸せホルモン」として、心や睡眠によい働きをしてくれる訳です。
一方、腸で吸収されたトリプトファンは他にもキヌレニンという成分を作ります。キヌレニン代謝は腸内細菌によって行われ、血液によって運ばれたキヌレニンは血液脳関門を通ります。そして、血液脳関門を通ったキヌレニンのさらなる代謝産物の一部は、神経毒素を持ち、うつだけでなく、統合失調症や、パーキンソン病に関与すると言われています。腸内でキヌレニンが沢山作られると、脳内セロトニンの生成が少なくなります。
こうした腸内の過剰代謝の一因は、腸内細菌の悪環境によると言われています。
というわけで、噂もまんざらではなさそうです。
やはり、気持ちの安定、さらに良い睡眠に対して、腸内環境を整える事は大切である、ということが言えそうですね。
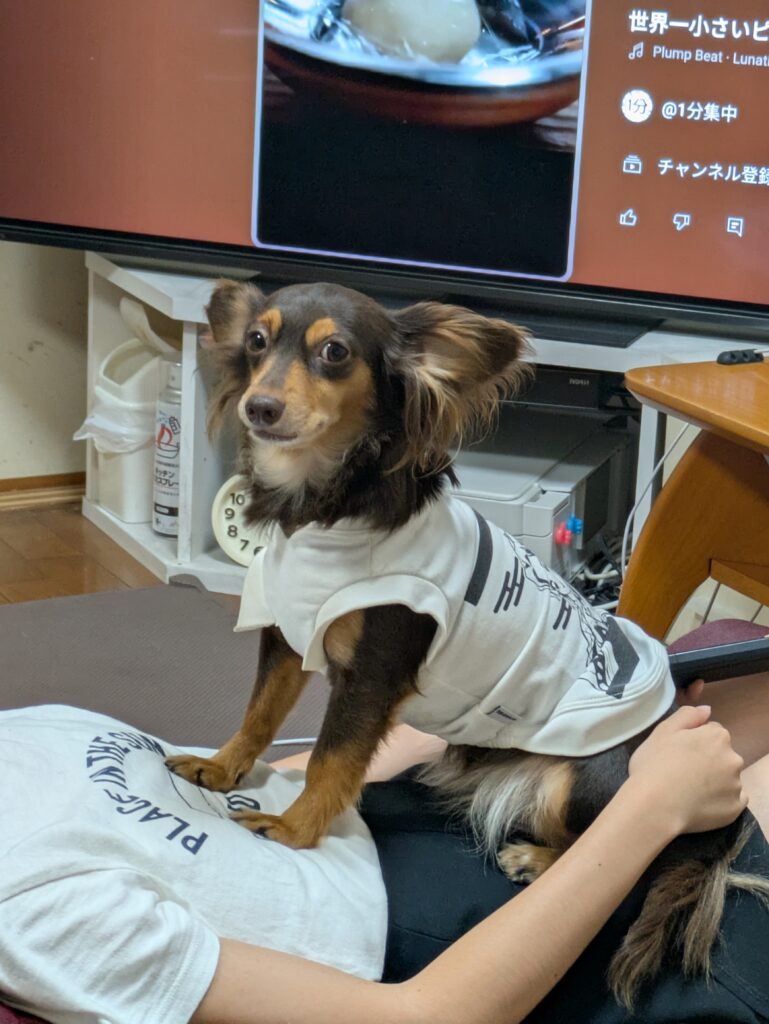


コメント